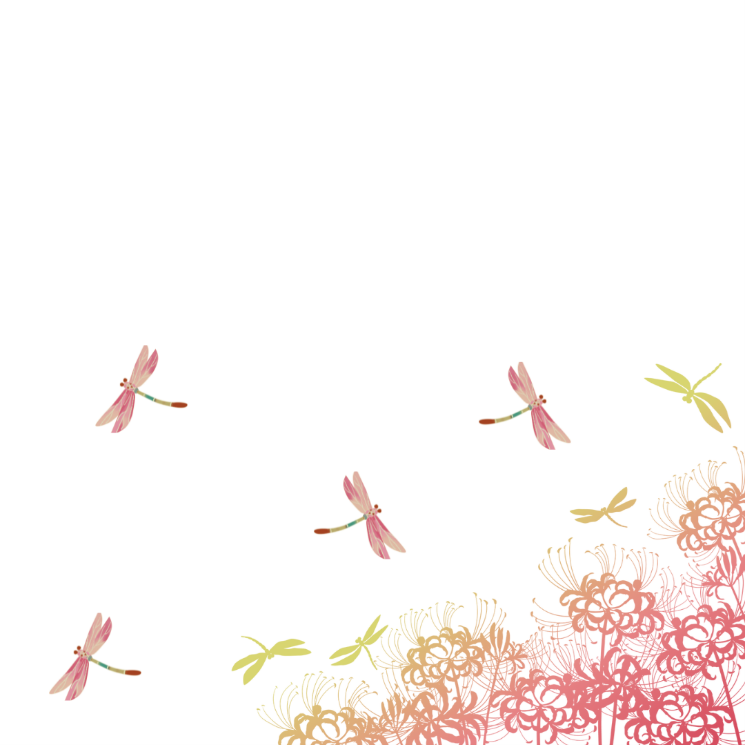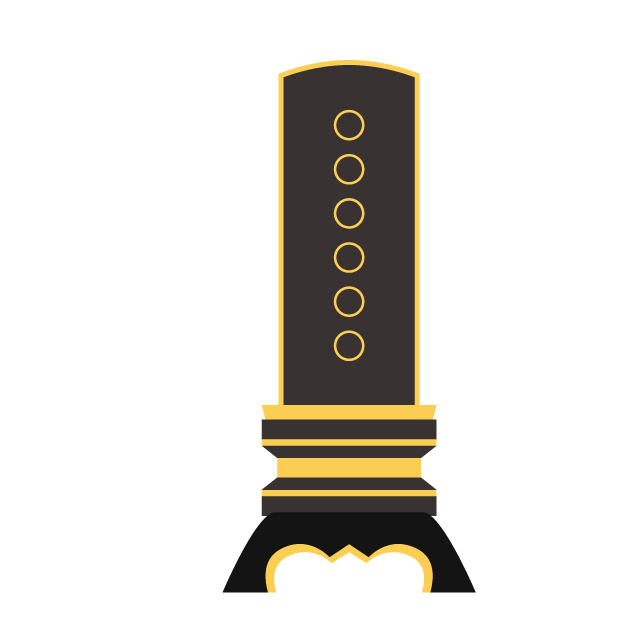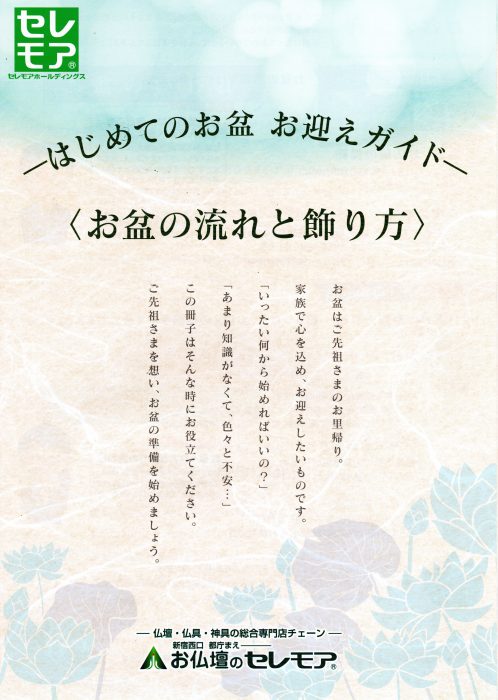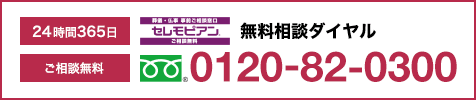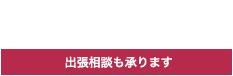「喪中はがき」とは?
「喪中はがき」は、故人が亡くなったことを知らせるものではなく、年賀状を出せないことを伝えるための「年賀欠礼状」という挨拶状です。
新年の挨拶を控えさせていただくというお詫びなので、毎年、年賀状をやり取りしている方には必ず「喪中はがき」を出すようにしましょう。
「喪中はがき」の対象になる親族の範囲
喪に服すべき親族の範囲については、一般的には二親等以内の親族といわれています。
範囲については厳密な決まりがあるわけではありませんので、別世帯であっても親しくしていた親戚や、故人に特別な想いがあり喪に服したいという意向がある時は、喪中はがきを出される場合もあります。
親戚にも送るのでしょうか?
最近では、喪中である身内同士でのやり取りを省略する場合もありますが、喪中はがきの本来の意味は年賀状を出せないご挨拶状です。普段から年賀状のやり取りをされている親戚には出されるとよいでしょう。
葬儀に参列してくださった方にも送るのでしょうか?
葬儀に参列していただいた方にも「喪中はがき」を送るのがよろしいとされています。
喪中はがきはいつまでに出すの?
年賀状は毎年11月1日から発売されます。そのため喪中はがきは一般的に、10月中旬から11月初旬までには出すようにしましょう。あまり遅くなると年賀状の準備を始めてしまわれる心配があります。できるだけ早いほうがよいでしょう。私製で喪中はがきを作られた場合に貼る切手は、基本的には弔事用の切手を使います。
2024年10月に「喪中はがき(胡蝶蘭)」が廃止されました。
通常はがきを弔事用に使われても何ら差支えはございませんが、弔事用の切手に「85円普通切手・菊」がありますので喪中はがきは私製で作られてこちらを使われてもよろしいでしょう。
ビジネス上の関係者にも送るのでしょうか?
ビジネス上でもプライベートな関わりがある方は「喪中はがき」を送るようにしましょう。
最近は「プライベートと仕事を分ける」というお考えの方も増えてきていますので、通常通り年賀状を送付するという場合も少しずつ増えています。