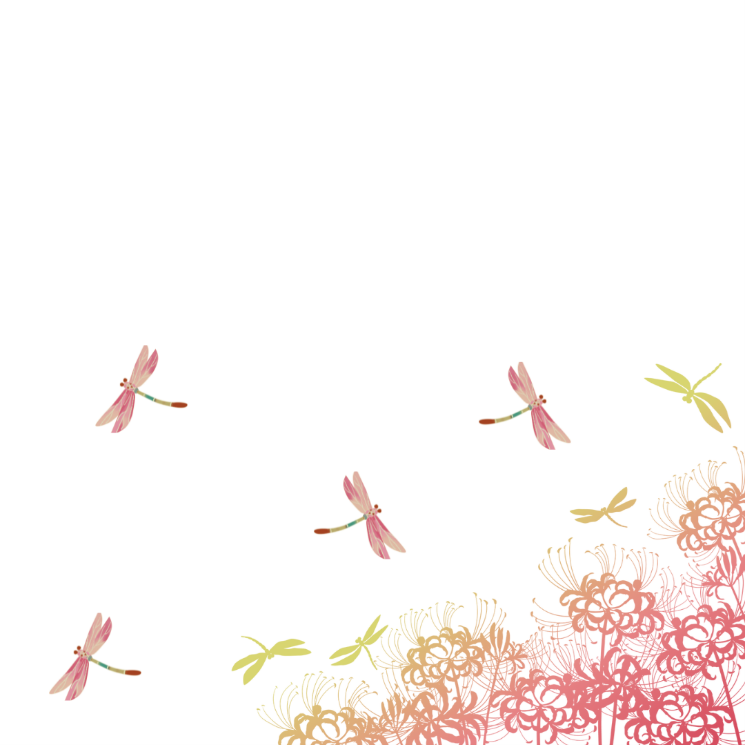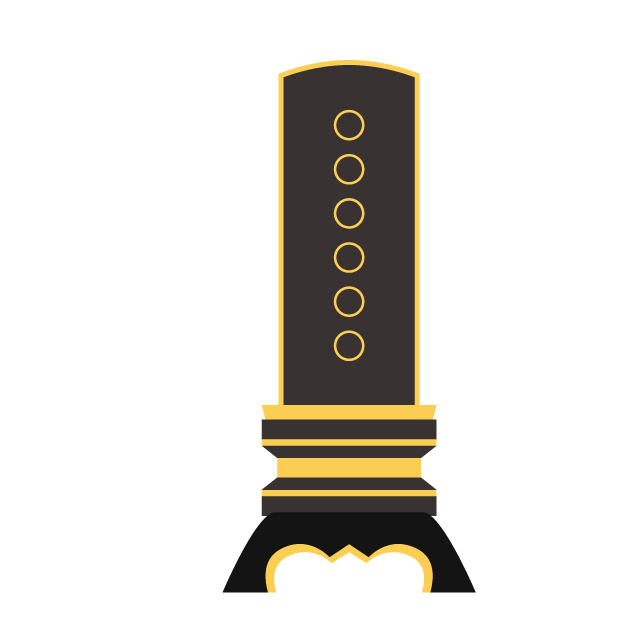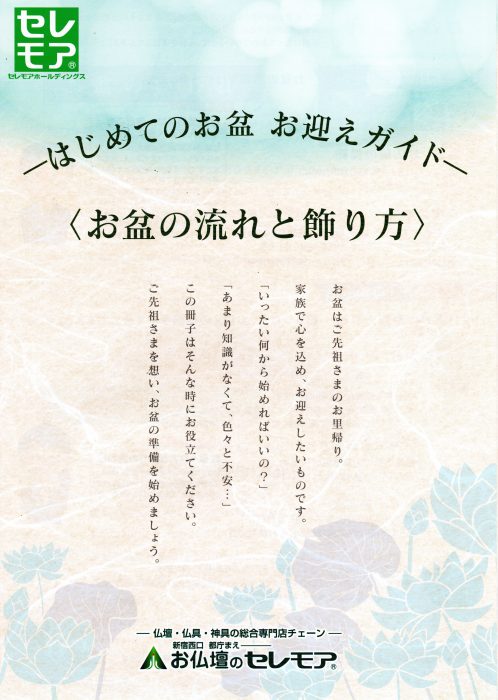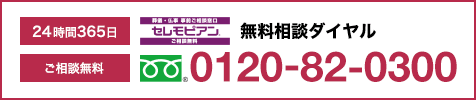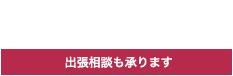自分自身が喪中であるが、年賀状をいただいてしまった。
お返事はお出しするようにしましょう。
喪中であることをお知らせしたくない場合は、通常通り年賀状を送りましょう。
喪中であることをお知らせする場合は、寒中御見舞いを兼ねて喪中をお知らせするとよいでしょう。
文面の例として末尾に、(昨年 秋に○○を亡くし 喪に服しておりますので年頭のご挨拶をご遠慮申し上げました)等お入れしましょう。
「寒中御見舞い」はいつでも出していいの?

出す時期は、「松の内」(1月1日~7日)が明けてからから立春(2月4日頃)までの間です。
「松の内」が明ける定義は地域の慣習でも変わります。
関西では1月15日、1月10日とされているところもありますが多くは1月8日からです。
「寒中御見舞い」の文例は?

文例1
寒中御見舞い申し上げます
このたびは丁寧なお年始状をいただきありがとうございました
私どもからご挨拶申し上げるべきところではございますが
喪中につき控えさせていただきました
今年もご厚誼賜りますようお願いいたします
文例2
寒中御見舞い申し上げます
ご丁寧なお年始状をいただきましてありがとうございました
昨年 〇月に○○が永眠いたしましたので
年頭のご挨拶を失礼させていただきました
旧年中にお知らせ申し上げるべきところ
年を越してしまいました非礼をお詫び申し上げます
寒さ厳しき折から皆様のご健勝をお祈り申し上げます
文例3
寒中御伺い申し上げます
向寒の候 皆様いかがお過ごしでしょうか
喪中のため 新年のご挨拶を控えさせていただきました
欠礼のお知らせが行き届かず誠に申し訳ございません
本年も何卒よろしくお願い申し上げます