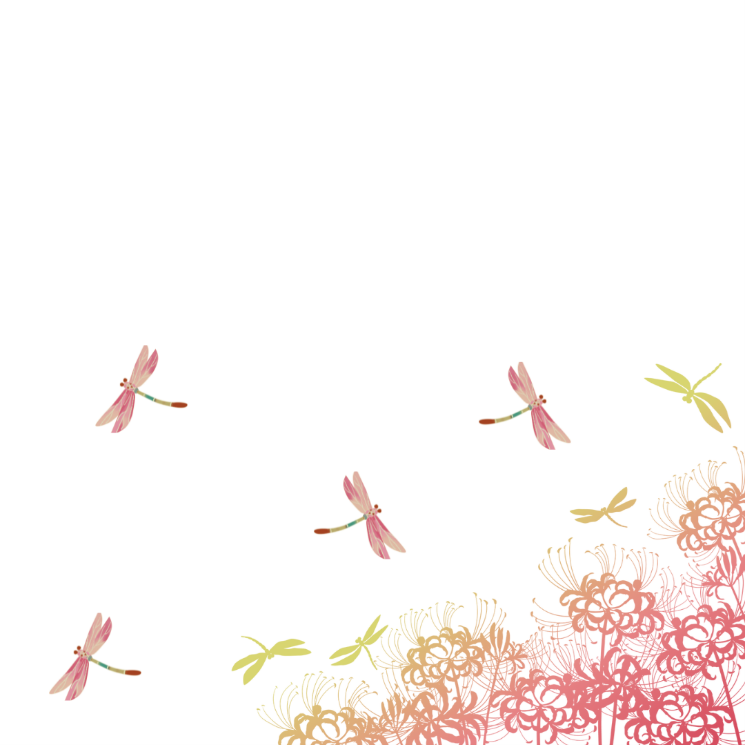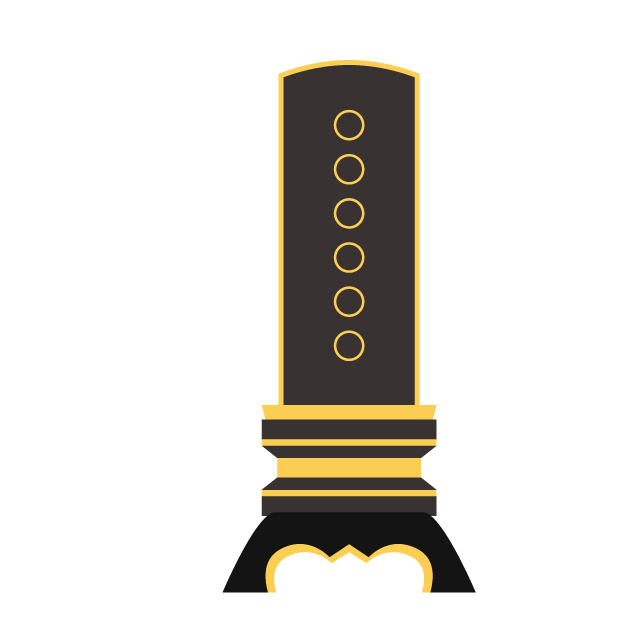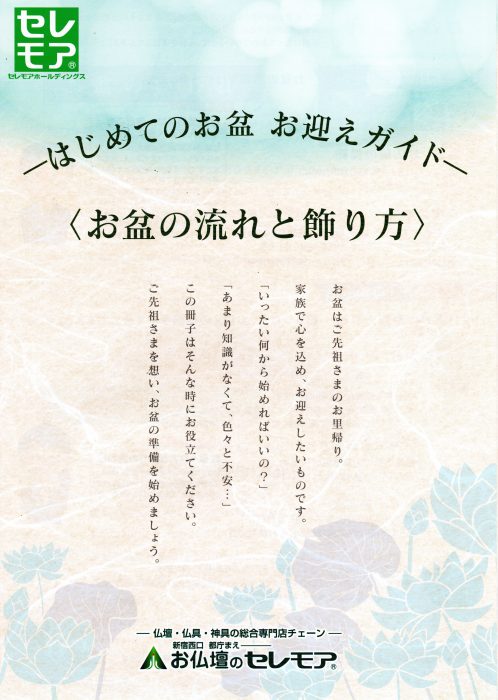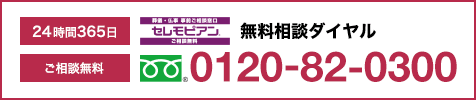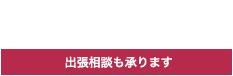お香典返しはいつごろまでにするの?
お香典返しは、「故人様に関する弔事が滞りなく終わりました」という報告とお礼を兼ねたものとして、
四十九日法要の終了後にお届けします。忌明け(四十九日)の翌日から、1か月くらいの間に先様に届くようにご用意されるとよいと言われています。
お香典返しは仏教の慣習ですが、神式やキリスト教式の葬儀を行った場合でも同様にご用意することが
一般的です。亡くなられてから1か月くらいを目安にお届けされる方が多くいらっしゃいます。
お香典返しのご挨拶状は必ず必要ですか?
お香典返しを配送される場合は、ご挨拶状をご用意された方がよいでしょう。
お香典返しを直接、渡される場合には、ご挨拶状は不要とされています。
ただし、葬儀当日にお香典返しを行う「当日返し(即日返し)」の場合にはご挨拶状をお付けすることがほとんどです。
百貨店のギフトサロンなどでお香典返しの手配をされますと、ご挨拶状も一緒に依頼ができます。
依頼される場合は、書式や価格などをよくご確認ください。
礼状を作成する期間も考えて早めに手配をされることをおすすめいたします。
当日返し(即日返し)とは何ですか?
葬儀のお帰りの際に渡す、つまり当日にお礼の気持ちを込めて直接香典返しを行うことです。
その場ですぐにお礼の気持ちをお伝えできることと、後日送付する手間が省けることがメリットになり、こちらを選ばれる方も増えてきました。
しかし、当日返しにした場合、参列者へお渡しする品物は香典の金額に関係なく、同じ品物になります。
それでは気が済まないと、高額なお香典を頂いた際は、後日忌明け後に挨拶状を添えて差額分のお返しをされる方が多くいらっしゃいます。
お香典返しで気をつけることはありますか?
忌明けが年末年始にかかる場合は、大晦日や松の内(関東1/1~7・関西1/1~15)を避けて、先様に届くように送るとよいでしょう。
年をまたぐ場合は、「仏事(弔事)は早めに繰り上げて行うことがよい」という考えから忌明けを待たずに年内にお返しをされる方もいらっしゃいます。