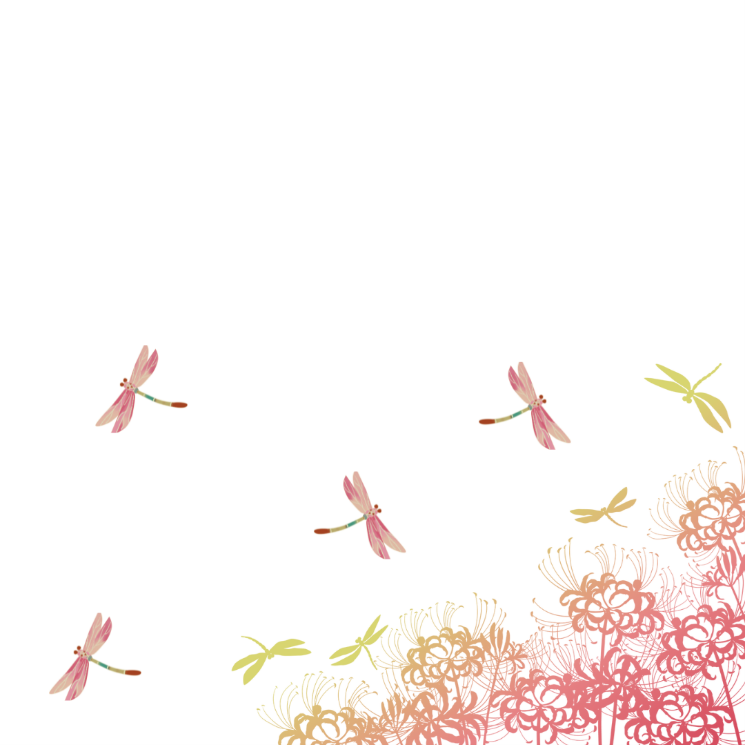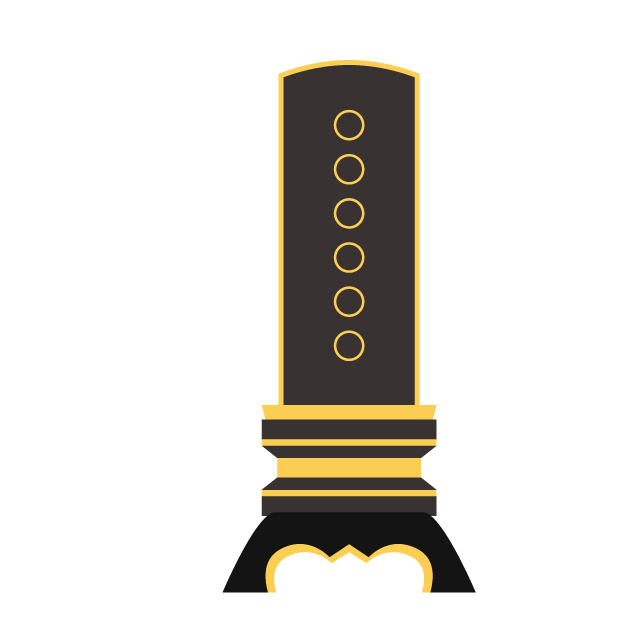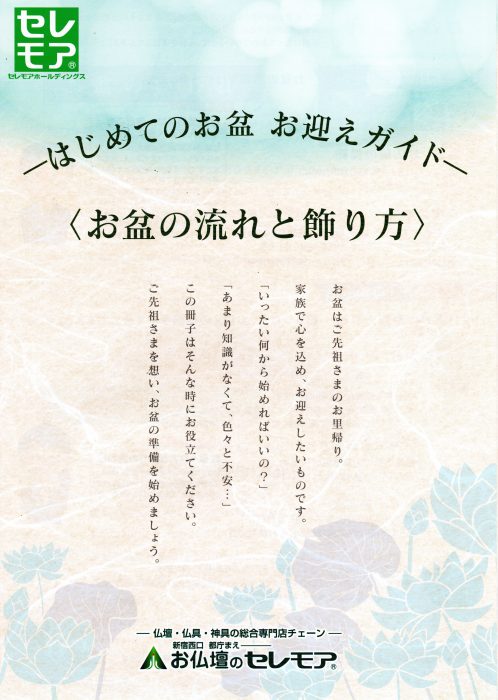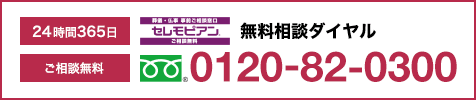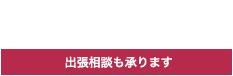お彼岸とは?
「彼岸(ひがん)とは、仏教用語で現世を表す「此岸(しがん)」に対して、向こう岸である極楽浄土を表す言葉です。
お彼岸にお墓参りをするのはどうして?
お彼岸は、春分の日・秋分の日を中日として前後3日間、あわせて7日間をいいます。初日を「彼岸の入り」、最終日を「彼岸明け」と呼び、この期間にお墓参りをするのが昔からの習わしです。
春分・秋分の日は昼と夜の長さがほぼ同じで、自然の節目をあらわします。春はこれから日が長くなり、秋は日が短くなっていきます。古くから農耕の区切りとも重なる大切な時期で、太陽をまつり、自然の恵みやご先祖さまへの感謝を表す行事として根付いたといわれています。
お盆が「ご先祖を家にお迎えする行事」であるのに対し、お彼岸は「ご先祖に会いにゆく行事」とされることもあり、少し意味合いが異なります。
神道にお彼岸はないの?
「お彼岸は仏教の行事だから、神道にはないのでは?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
実は神道においても、お彼岸は大切な時期とされています。
神道では自然そのものに神々が宿ると考えられており、人は自然と共に生き、感謝の気持ちを忘れずに過ごすことを大切にします。お彼岸は、自然界とつながり、ご先祖さまを通して自然の恵みに感謝し、日々の平穏を祈る特別な機会とされています。
このように、お彼岸は宗教や地域の違いを超えて、自然とご先祖さまに感謝をささげる大切な行事として受け継がれてきました。お墓参りに足を運ぶことは、ご家族の心をつなぐ機会にもなるのではないでしょうか。