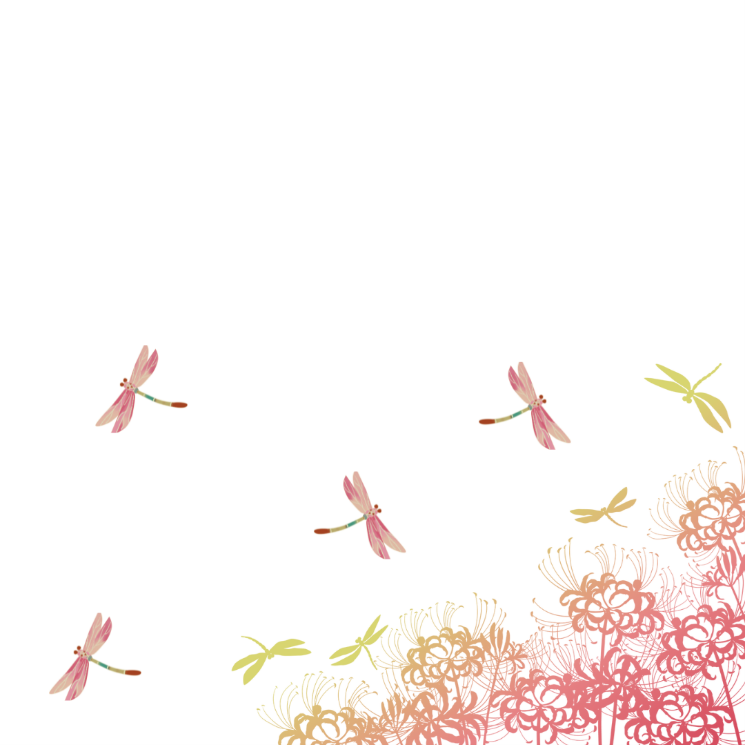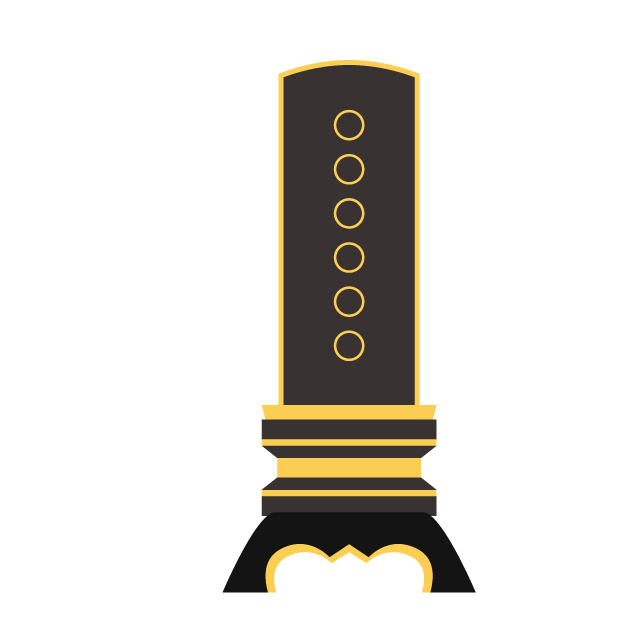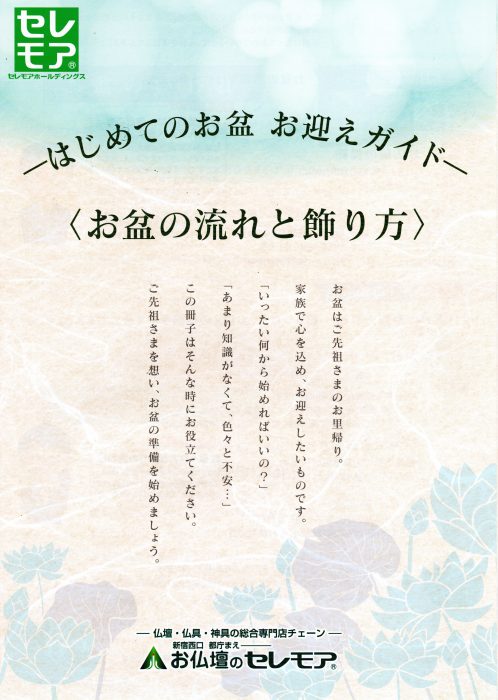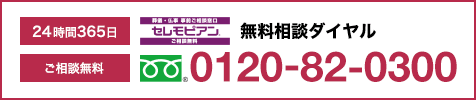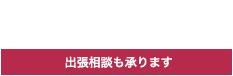おはぎとぼたもち ― 呼び名に込められた意味
お彼岸のお供え物として親しまれてきた「ぼたもち」と「おはぎ」。今では区別なく呼ばれることも多いですが、もともとは季節によって呼び名や形に違いがありました。
おはぎとぼたもち ― 季節の呼び名
お彼岸といえば欠かせないのが「おはぎ」と「ぼたもち」。実は春と秋で呼び名が分かれていたことをご存じでしょうか。春は牡丹の花に見立てた「ぼたもち」、秋は萩の花になぞらえた「おはぎ」と呼ばれます。夏は「夜船」、冬は「北窓」と、四季に応じた名も残っています。
形やあんこにも違いがあり、春は丸くこしあん、秋は俵型で粒あんが一般的でした。今では保存技術の進歩であんこの種類を問わず作られるため、違いはあいまいになっています。
さらに地域によっても呼び方はさまざま。もち米なら「ぼたもち」、うるち米なら「おはぎ」と分ける所や、きな粉とあんこで呼び分ける所もあります。中にはご飯の潰し方で「半殺し」「皆殺し」と表現する地域まであるそうです。
お彼岸に食べられる理由
赤い小豆には古くから魔除けの力があるとされ、先祖供養や五穀豊穣を祈る食べ物として用いられてきました。
春の彼岸は農作業の始まりに、秋の彼岸は収穫への感謝を込めて、ぼたもちやおはぎが供えられてきたのです。
おはぎやぼたもちは、先祖への感謝や無病息災を願う心が込められたお供え物です。お彼岸に召し上がる際には由来や呼び名に触れることで、ご供養の時間がより深いものとなるでしょう。