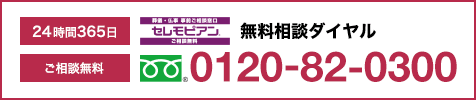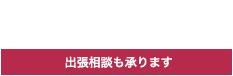すべて

公開日2022/12/21
更新日2023/05/22
喪中のご挨拶 年賀状を出してしまったときは?
年賀状を投函してしまったあとにその方から年賀欠礼状(喪中はがき)が届いた場合は、すぐにお悔みとともにお詫びの連絡をするようにしましょう。電話のみでも大丈夫ですが、年が明けてから寒中御見舞いなどであらためてお悔やみの言葉を述べるとより丁寧でしょう。
新年になってからわかった場合も同様です。
もっと読む

公開日2022/12/19
更新日2022/12/28
喪中のご挨拶 年賀状をいただいたら
お返事はお出しするようにしましょう。喪中であることをお知らせしたくない場合は、通常通り年賀状を送りましょう。
喪中であることをお知らせする場合は、寒中御見舞いを兼ねて喪中をお知らせするとよいでしょう。文面の例として末尾に、(昨年 秋に○○を亡くし 喪に服しておりますので年頭のご挨拶をご遠慮申し上げました)等お入れしましょう。
もっと読む
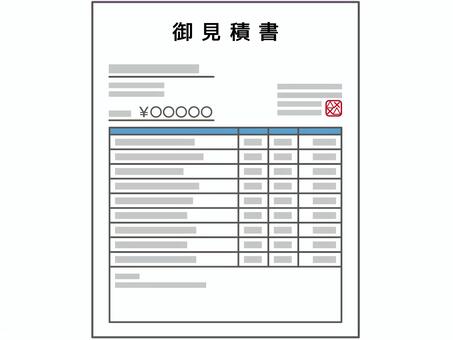
公開日2022/12/16
更新日2023/04/28
葬儀費用の見積書を手にしたら
葬儀の費用は、大きく4項目に分かれます。
・祭壇や棺など葬儀自体の直接的な費用
・宗教儀礼費用、飲食などおもてなし費用
・会館やホールなどの葬儀施設の使用料金
・火葬料金などです。
お葬儀をお身内やごく親しい方たちでする「家族葬」にするか、故人様や喪主様と関係のある方々もお呼びする「一般葬」にするか参列者の人数などにより、葬儀費用は変わってきます。
葬儀社のホームページ上で葬儀にかかる費用のプランを公開している場合が多く、それらを比較することで大まかな相場がわかります。
料金プランは、祭壇や棺など葬儀に必要な項目をパッケージ化して基本料金に据えて、そこに飲食や返礼品などのサービスが加わることを示しているところがほとんどです。ただ、葬儀社によって基本料金に含まれているものは異なりますので、何が含まれていて、何が含まれていないのかを見比べ、確認しておくことが大切です。
また、追加で発生する可能性がある飲食や返礼品など主におもてなしにかかる商品やサービス、変動する可能性がある搬送料やご安置施設などの料金項目についても確認しておきましょう。
見積もりには専門用語が多用されていないか、使われていたとしても説明が付記してあるか、パンフレットの写真や図、表などが解りやすいかどうかもチェックします。
もっと読む

公開日2022/12/16
更新日2022/12/28
仏壇・仏具のお手入れはどうすればいいの?
ろうそくやお線香から出る油煙や煙、脂(ヤニ)、そしてホコリです。人の手から付くわずかな汗の塩分も長い間に金属の錆(サビ)の原因になります。
もっと読む

公開日2022/12/16
更新日2023/05/17
今どきの生前整理 デジタル情報の整理
「物」ではないため忘れがちになりますがデジタル情報の整理も大切です。
パソコンやスマートフォン内にある写真やメールなどのデータをはじめ、SNS・銀行口座・証券口座などのログインIDやパスワードといった、近年において重要度を増してきた「デジタル情報」は、ご家族に知らすべき個人情報と、そうでないものはしっかりと整理しておきましょう。これはご自身で判断することが困難になった場合も前提に考えます。
ログインIDやパスワードが分からなくてお悩みのご家族は少なくありません。そのような情報を取り出す専門の業者もありますが作業は困難で、必ず全て成功するとは限らず、日数も費用もかかります。
ご自身とご家族の為にも、エンディングノートなどに「デジタル情報」や「情報の保存方法」など分かりやすくしっかりと整理しておきましょう。
もっと読む

公開日2022/12/16
更新日2023/04/28
生前整理のおすすめ
終活は「人生の終わりのための活動」です。
その中には生前整理も含まれると考えてもよいでしょう。
「生前整理」にまだ早すぎる、もう遅い、はありません。
お子様が独立されるなどで家族構成が変わった時期は好機かもしれません。
もっと読む

公開日2022/11/25
更新日2024/02/07
いつまでも一緒にペットのご供養
お線香をはじめペット専用のお悔やみの品は、近年随分と充実してまいりました。虹の橋をイメージしたカラフルな肉球型のロウソクやお花畑柄のお線香もあります。
ペットは亡くなると天国の少し手前にある虹の橋のたもとで楽しく過ごしながら、やがて来る飼い主を待っているといういわれています。
香りは、お花畑をイメージしたフルーティーフローラルな香りや森林の香りも人気です。お香、香立てそしてロウソクがセットになっている商品は香炉や灰がなくても直ぐにご供養ができます。
お近くのセレモアの仏壇店にご相談くださいませ。
もっと読む
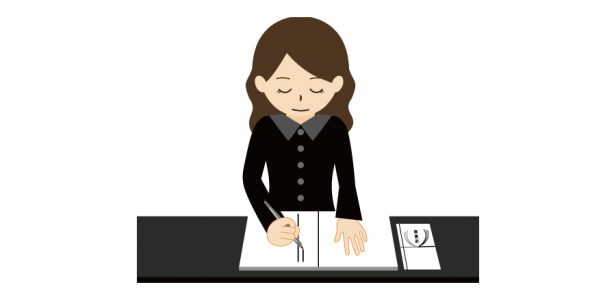
公開日2022/11/25
更新日2023/05/16
お香典のお悩み いつお持ちすればいいの?
両日参列する場合は、通夜式にお香典を持参することが多いようです。葬儀・告別式の際には記帳のみします。
もっと読む
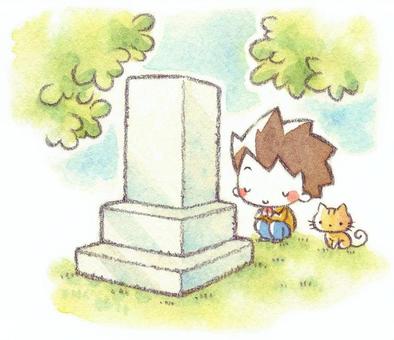
公開日2022/11/18
更新日2023/05/19
ペットと一緒に入れるお墓
最近はペットを家族同様に慈しんで飼われている方が多くいらっしゃいます。ペットが亡くなったときには一緒のお墓に入れたいと望まれるお声も少なくありません。
最近では家族のお墓にペットも一緒に入れて永遠に眠ることができる、そのような区画のある霊園も増えてきました。
もっと読む

公開日2022/11/17
更新日2023/05/31
お香典のお悩み 送るときはどうすればいいの?
郵送される場合は、不祝儀袋に入れてから現金書留封筒で郵便局から出します。
もっと読む